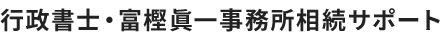【横浜市】遺産相続に関わる手続きや相続税対策は行政書士に相談して税金を抑えよう!
横浜で被相続人が亡くなり遺産相続をする際には、相続税を納めなければなりません。相続税の軽減方法は多岐に渡り、生前からの対策も可能です。相続税のことなら専門の税理士へご相談ください。
遺産相続で発生する税金を抑えるポイントを解説

亡くなられた被相続人から遺産を受け取る場合には、その相続した財産には税金を納めなければなりません。
ただし、遺産相続の際の相続税はすべてのケースで発生するわけではないのです。
相続税には基礎控除が3,000万円設定されており、さらに「法定相続人数×600万円」が控除の対象となります。
つまり、相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円までは相続税は実質0円です。
しかし、土地や家屋などが含まれる遺産総額は基礎控除額を超える場合も多く、税金の対象となってしまいます。
相続税は被相続人が亡くなることにより突然発生します。
遺産を相続するためには納付するべき税金ですが、同時にできるだけ節税をして納付額を低く抑えたいと考える方も多いのではないでしょうか。
遺産相続によって発生する税金を抑えるポイントを3点ご紹介します。
利用したい控除と特例
基礎控除として「3,000万円+相続人数×600万円」までの遺産総額には相続税は発生しません。
また、基礎控除額を超過した遺産に対しても様々な控除や特例が用意されています。
1:配偶者控除
配偶者が相続人に含まれる場合は1億6千万円まで、あるいは法定相続分に相当する財産額までが非課税です。
2:贈与税額控除
相続が開始となる3年前まで遡って贈与した財産の金額を課税に加算しますが、既に支払っている贈与税に関しては相続税から控除されます。
3:未成年者控除
未成年が相続人となった場合、成人に至るまでの年数に10万円をかけた金額が控除対象です。
例えば、相続人が10歳の場合は10年×10万円=100万円が控除の対象となります。
4:相次相続控除
相次相続とは、遺産相続が開始され分割協議が完了する前に相続人の中の1人が亡くなり、新たな遺産相続が開始されることです。
2回目以降の相続は控除の対象となります。
5:外国税額控除
国外で保有されている資産に対して、すでに相続税に相当する税金を納付している場合は、日本での相続税は控除されます。
外国税額控除には複雑な計算が必要ですので、適用する際には専門家のサポートが必要です。
さらに、控除のほかにも特例と呼ばれる制度も節税に活かすことができます。
1:小規模宅地の特例
一定の要件を満たした場合に、相続する土地の相続税評価額を最大80%減額することができます。
2:家なき子特例
小規模宅地特例を同居していなかった親族も受けることができる特例です。
非課税制度を利用する
相続税の対象となる遺産とは、基本的に売却した際に価値があるもののことです。
また、以下の4つの項目に関しては非課税財産とみなされ、相続税の対象から除外されます。
- 墓地、仏壇、仏像、神棚など
- 国家や公共団体に寄贈した物品
- 非課税枠内の保険金(500万円×法定相続人数)
- 非課税枠内の退職金(500万円×法定相続人数)
生前にできる相続税対策
上記で解説した控除、特例、非課税制度のほかにも生前から準備することで節税効果を生み出すことができる対策があります。
・生前贈与
生前贈与とは亡くなる前に個人から個人へ財産を譲り渡す行為です。
この場合、相続税は発生しませんが贈与税の対象となります。
贈与税に対する対策は、暦年課税制度や相続時精算課税制度などです。
・非課税財産を生前に購入する
仏壇、墓地などの非課税財産を生前に購入しておくことで非課税対象が拡大します。
・教育資金贈与信託
信託銀行などに子どもや孫の教育資金を信託した場合、1,500万円までの贈与税が非課税の対象です。
相続税の負担をできるだけ軽減する方法は上記の要件以外にも考えられます。
しかし相続人が個人で対策を検討することは非常にハードルが高く、専門家のサポートは欠かせません。
相続人の遺留分を考慮した遺産分割や必要な手続きから相続税対策まで、地域密着型で相続手続きをサポートする行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにご相談ください。
相続税対策のご相談なら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

家族の大黒柱が亡くなり遺産を相続するという事態は、突然訪れる可能性があります。
被相続人の財産は相続人が協議のうえ相続しますが、その際に発生する相続税は予想外に高額になり戸惑ってしまうというケースも少なくはありません。
遺産を継承する際には対象となる相続税は納付しなければなりません。できるだけ納付額を軽減したいものです。
相続税の軽減に関しては、配偶者や未成年を対象とした控除をはじめ各種控除や特例の活用が考えられます。また生前贈与や教育資金贈与信託など、生前から準備できる対策もあります。
しかし、相続税対策では複雑な計算を行ったうえで申告をしなければなりません。相続税の節税対策を確実に行うためには、専門家のサポートが何よりも重要です。
横浜市で遺産相続に関してのご相談は、地域密着型で相続手続きをサポートする行政書士・富樫眞一事務所相続サポートにお問い合わせください。
遺産相続に関するお役立ちコラム
- 【横浜】遺産相続で行政書士に依頼できる手続きとは?
- 【横浜】遺産相続の依頼は事前に!相続放棄の失敗事例を紹介
- 【横浜】遺産相続で兄弟間に起こるトラブル例について
- 【横浜】遺産相続における書類作成の注意点
- 横浜で相続相談!遺産分割の対象となる財産とは?
- 【横浜】相続相談に対応!名義変更の期間について
- 【横浜】相続相談における手続きの流れを解説
- 【横浜で相続相談】相続トラブルの要因と対処法
- 【横浜市】遺産相続の期限が迫っている際の対策法とは?
- 【横浜市】遺産相続でトラブルを防ぐための方法とは?
- 【横浜市で遺産相続】兄弟に遺留分はある?
- 【横浜市】遺産相続でかかる税金を抑えるポイントとは?
- 【横浜市で相続相談】不動産相続について相談する際の注意点
- 横浜市で相続相談!遺産分割協議後に遺産を発見した場合について
- 横浜市で相続相談!遺留分と法定相続分の違いについて
- 【横浜市で相続相談】生前にできる対策とは?流れや手続きも事前に相談!