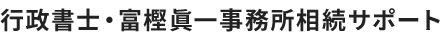相続人になったのに、遺言や生前贈与などで他の人に財産が渡ってしまった…。このような場合に、最低限の財産を取り戻すための手段が遺留分侵害額請求権です。この記事では遺留分の仕組みから遺留分侵害額請求権を行使する方法まで解説していきます。
遺産相続と遺留分の関係
遺産相続の現場では、「すべての遺産を子のひとりに与える」とか「相続人以外の人に財産の大部分を譲る」といった極端な遺言が問題になることがあります。
もちろん遺言の内容は被相続人が自由に決められるため、このような遺言も有効です。しかし財産を受け取れなかった相続人にとっては、こうした相続は不公平に感じられることでしょう。そのようなときに活用できるのが「遺留分」です。
遺留分とは
遺留分とは相続人に認められた「最低限の相続分」のことです。たとえ遺言書でも遺留分を変えたり無効にしたりできないため、遺留分が与えられた相続人は、他の相続人や相続人以外の人にすべての財産が与えられた場合でもその人から遺留分相当額を取り戻すことができます。
遺留分を持つ相続人
民法第1042条によると、遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。つまり、
- 配偶者
- 子(および代襲相続人)
- 直系尊属
のそれぞれが遺留分の権利を持つ相続人となります。
遺留分が侵害されるケース
遺留分が侵害されるのは、主に次のような場面です。
- 遺言書による指定:たとえば配偶者や複数の子がいるにもかかわらず長男にすべての財産を相続させるとか、法定相続人がいるのに第三者にすべての財産を遺贈するといったケース
- 生前贈与:被相続人が生前、特定の相続人や第三者に財産の大部分を贈与してしまうケース
- 死因贈与:死因贈与契約により、特定の相続人や第三者に財産の大部分を贈与してしまうケース
なお相続人への生前贈与は原則として「相続開始前の10年間」、第三者への生前贈与は「相続開始前の1年間」に行われたものに限り遺留分の侵害とみなされます。
遺留分侵害額請求権について
遺留分が侵害された相続人は、被相続人の財産を譲り受けた人(受遺者・受贈者)に対して「遺留分侵害額請求権」を行使できます。
遺留分侵害額請求権とは、受け取れなかった遺留分(=遺留分 − 実際に相続した額)に相当する金銭の支払いを求める権利です。民法第1046条第1項には次のように規定されています。
|
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。 |
遺留分減殺請求権との違い
遺留分侵害額請求権が2019年7月1日の民法改正によって誕生した権利で、それ以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれる似たような権利がありました。遺留分減殺請求権と遺留分侵害額請求権の違いは次の表の通りです。
| 遺留分減殺請求権 (2019年6月まで) |
遺留分侵害額請求権 (2019年7月から) |
|
| 遺留分侵害部分の精算方法 | 物件の返還(原則) 金銭で精算(例外) |
金銭で精算のみ |
| 遺留分侵害の対象となる生前贈与 | 制限なし | 直近10年間のみ |
| 侵害額の支払い猶予 | なし (すぐに遅延損害金が発生) |
裁判所の判断により設定 |
過去の相続手続などを通して旧制度(遺留分減殺請求権)を知っていた方は、新しい制度(遺留分侵害額請求権)で変わった部分に十分注意してください。
遺留分侵害額請求権の時効
民法第1048条の規定によると、遺留分侵害額請求権には「時効」があります。
|
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。 |
このように、遺留分侵害額請求権の時効は遺留分の侵害を知ってから1年、あるいは(遺留分の侵害を知らないままの場合)相続開始から10年です。
関連記事:『遺産相続の時効とは?権利や手続きの時効について解説』
侵害額の算定方法
遺留分侵害額請求権は遺留分の侵害額に相当する金銭を請求する権利です。このため権利を行使するには、まず侵害額を算定しなければなりません。
遺留分の算定は次のステップで行います。
①遺留分割合を確認する
遺留分割合は、相続人の種類や組み合わせによって変わります(なお子と直系尊属が複数いる場合、遺留分をそれぞれの数で割ります)。
- 配偶者のみの場合:基準となる相続財産の2分の1
- 配偶者と子の場合:それぞれ基準となる相続財産の4分の1
- 配偶者と直系尊属の場合:配偶者は基準となる相続財産の3分の1、直系尊属は6分の1
- 子のみの場合:基準となる相続財産の2分の1
- 直系尊属のみの場合:基準となる相続財産の3分の1
②基準となる相続財産の確認
基準となる相続財産とは被相続人の相続財産に、死因贈与や相続開始前の一定期間(10年or1年)に行われた生前贈与の額を足して、そこから債務を引いたものです。ちなみに相続財産に不動産が含まれる場合、路線価や固定資産税評価額、実勢価格、地価工事価格などで金額を評価します。
③遺留分侵害額の計算を行う
上記①の遺留分割合と②の相続財産を掛け合わせて、相続人ごとの具体的な遺留分を計算します。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求権の行使にもいくつかのステップがあります(基本的には①から順に行っていきます)。
①当事者による話し合い
まずは当事者同士で直接話し合うのが原則です。お互い事情を丁寧に説明すれば、相手も納得して円満解決を計れるかもしれません。ただし場合によっては弁護士を間に入れて、専門家の意見を聞きながら話し合いを進めるケースもあります。
話し合いが合意に達したら合意書を作成し、内容に沿って金銭(遺留分侵害額)を支払います。
②内容証明郵便の送付
話し合いがまとまらない場合は内容証明郵便を送付します。「話し合いが決裂したのになぜ書面を送るの?」と不思議に感じるかもしれませんが、これはすでに説明した「時効」の完成を防ぐために必要なステップです。
内容証明郵便で時効完成までの期間が6か月伸びるため、その間に家庭裁判所への申し立てを準備します。
③遺留分侵害額の請求調停
家庭裁判所への申し立ては2種類ありますが、原則として最初に行うのが「遺留分侵害額の請求調停」です。
調停では調停委員と呼ばれる仲介役が当事者の間に入って話し合いをまとめたり、アドバイスを行います。当事者が調停案に合意すれば調停成立となり、合意内容に従って金銭(遺留分侵害額)が支払われます。
④遺留分侵害額請求訴訟
調停が不成立になった場合は、いよいよ遺留分侵害額請求訴訟の提起です。遺留分侵害額請求訴訟は話し合いではなく裁判手続なので、訴えた側も訴えられた側も証拠を提出したうえで、それぞれの主張を行います。なお一連の裁判手続は素人には難しいため、弁護士に依頼するのが一般的です。
裁判で訴えた側の主張が認められれば、判決として遺留分侵害額の支払い命令が出されます。判決には法的強制力があるため、もし相手が支払いを渋っても「差し押さえ」などの方法で金銭(遺留分侵害額)の回収が可能です。
遺留分侵害額請求を受けた場合
最後に「遺留分侵害額請求を受けた場合」の対応方法ですが、どのような事情があるにせよ、遺留分侵害額請求を放置(無視)するのは得策ではありません。
すでに説明した遺留分侵害額請求の4ステップのうち、どの方法で請求を受けても何らかのリアクションをすべきです。もし請求内容に納得できるなら早めに遺留分侵害額を支払った方がよいですし、納得できないなら話し合いで相手に説明する必要があります。
特に遺留分侵害額請求訴訟を放置すると「欠席裁判」となり、相手の言い分がそのまま判決内容となる可能性が高くなるため注意が必要です。
まとめ
遺留分侵害額請求権は、不公平な相続が行われた場合の「切り札」です。法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属の方は、相続財産のほとんどが一部の共同相続人や第三者に渡ってしまった場合にこの権利を行使し、最低限の相続分を取り戻すことができます。トラブルを最小限にするためにも弁護士などの専門家に相談しながら、納得のいく相続手続を目指してください。